羊と日本人〈書評〉
2024年2月2日
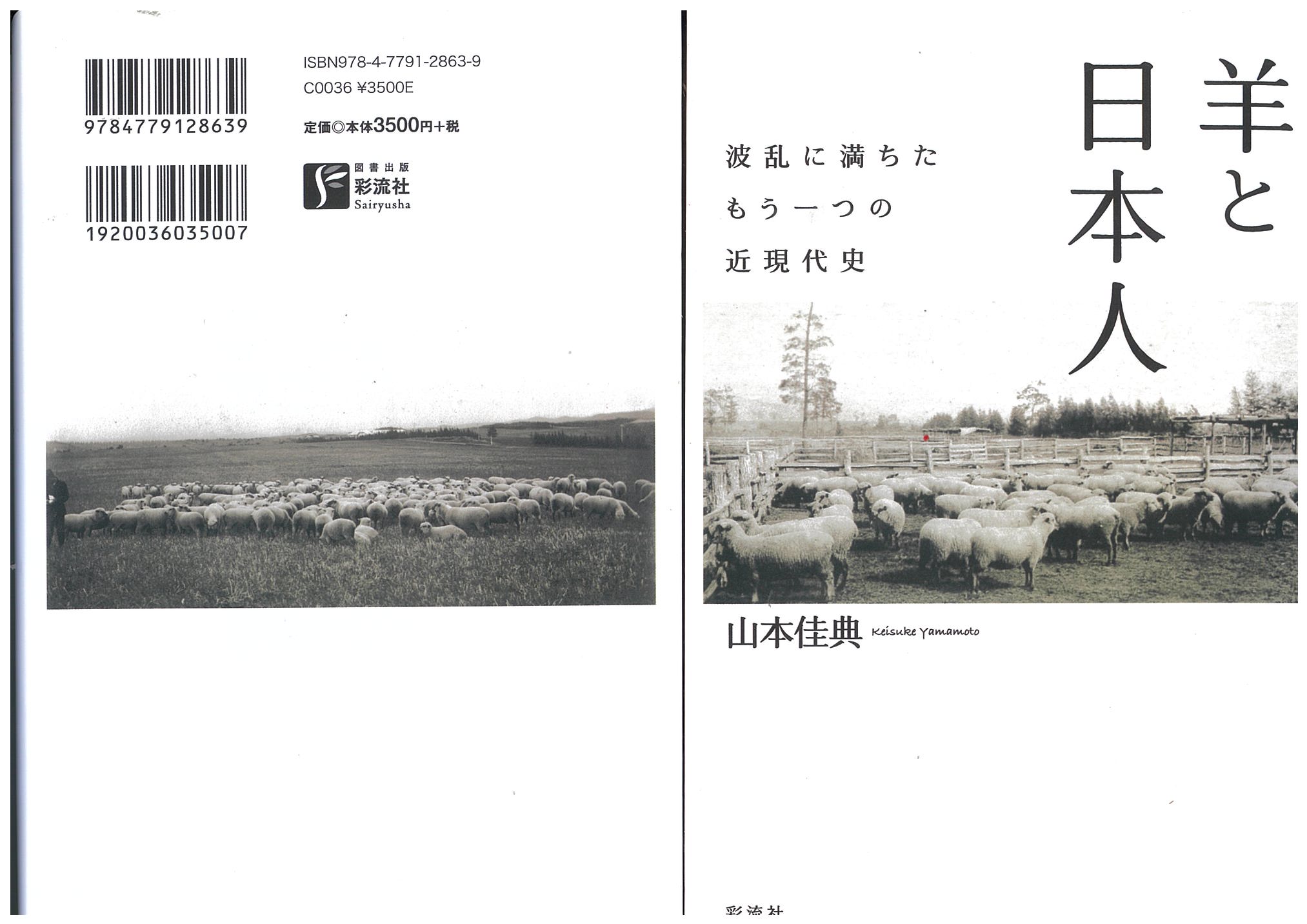
私が羊飼いを始める前に、鹿追町史の中に小室道郎という羊飼いについて触れた短い記述を発見した。その内容は大正15年に鹿追町の熊ノ沢付近に小室道郎が牧場を開設、豪州から輸入した数百頭の羊を、牧羊犬を使って放牧管理した。元々法律を学ぶため米国留学中に羊と出会い、帰国後滝川種羊場の技師を経て、同地に就農、豪放磊落な気質で、斗酒なお辞せず、その後、満州における綿羊の普及指導のため渡満して、昭和13年に閉場とあった。もちろん小室道郎については「羊と日本人」の中に詳しく記されている。
私はそのミステリアスな羊飼い像に憧憬を抱き、いつか調べてみたいと思っていたのだが、それがある日著者山本佳典さんの突然の訪問を受け、明治以降の羊の歴史を調べていると伺い、小室のことが頭に蘇り、その話を皮切りに、主に戦後のめん羊事情、現在の羊の状況について、時間を忘れて話し込んだ。巻末の参考資料を見てもらえば頷けると思うが、綿密な取材活動を元に史実を時系列にまとめていることで、この本は日本の羊の歴史書として価値づけられるのはもちろんのこと羊を通して、明治維新からの日本の歴史の背景を辿っている。またその羊史を人物にスポットを当て、登場する人物を一人一人その出自から調べ、ほとんどの方はすでに他界されているわけだが、現存されているお子さんお孫さん、親族にまで取材を試み、家族アルバムに保存されていた写真や、関連する新聞記事、日記までを顧み、その人物像を客観的にとらえることで、読者に実像を想像させてくれる潜在力がある。おそらくこの中に登場する人物の多くは著者が発掘しなければ、やがてファミリーヒストリーとして継承されることもなくなり、人々の記憶から消えていったであろう。その点でこの本はぎりぎりのタイミングで書かれたといえる。小室を例にとればご子息羊王太郎氏がご存命であることを調べ、何度か取材されている。私も著者と一緒に面談する機会を得た、父親に翻弄され苦労させられたことを話し、苦笑しながらも、草原に鈴蘭が咲き、羊が放牧されている風景を懐かしく語られて、なぜか安堵した。
本書の中に登場する人々の羊への思いの連鎖が我々現在の羊飼いへと繋がり、名も無き人々の幾多の苦労があって、わずか2万頭とはいえ、今日本に羊が絶えることなくいる事実を知り、胸が熱くなる。国策に翻弄されて、軍需目的で増減した羊ではあるが、大陸で活躍した羊人たちは、戦争を推進するのではなく、羊の普及に占領地の人々と羊という共通語での交流を求めていたように思える。その幾度かの増頭計画で、何万頭もの羊が輸入され、研究体制も整っていたことは羨ましくもある。
今の羊のおかれている状況は日本のめん羊史の中でも相当に不遇の時代ではあるが、羊に魅了される人々は絶えない。羊と何の関わりもなかった著者と羊との出会いも摩訶不思議であり、彼を突き動かせたものは何なのか、取材が進むにつれ、後戻りできなくなったのは羊の仕業に違いない。著書の最後で、なぜ羊を飼い続けるのか?との著者からの問いに対して、羊飼いからの曖昧な応えは経済的理由や生産物の多様性などの理屈よりも羊を「好きだから」という感情的な言葉だった、羊を飼う理由に理屈めいた答えはなく、家畜の中から羊を選ぶという行為こそ、その理由の本質が隠れているように思う。と結んでいる。現在の羊関係者必読の書である。
茶路めん羊牧場 武藤浩史


